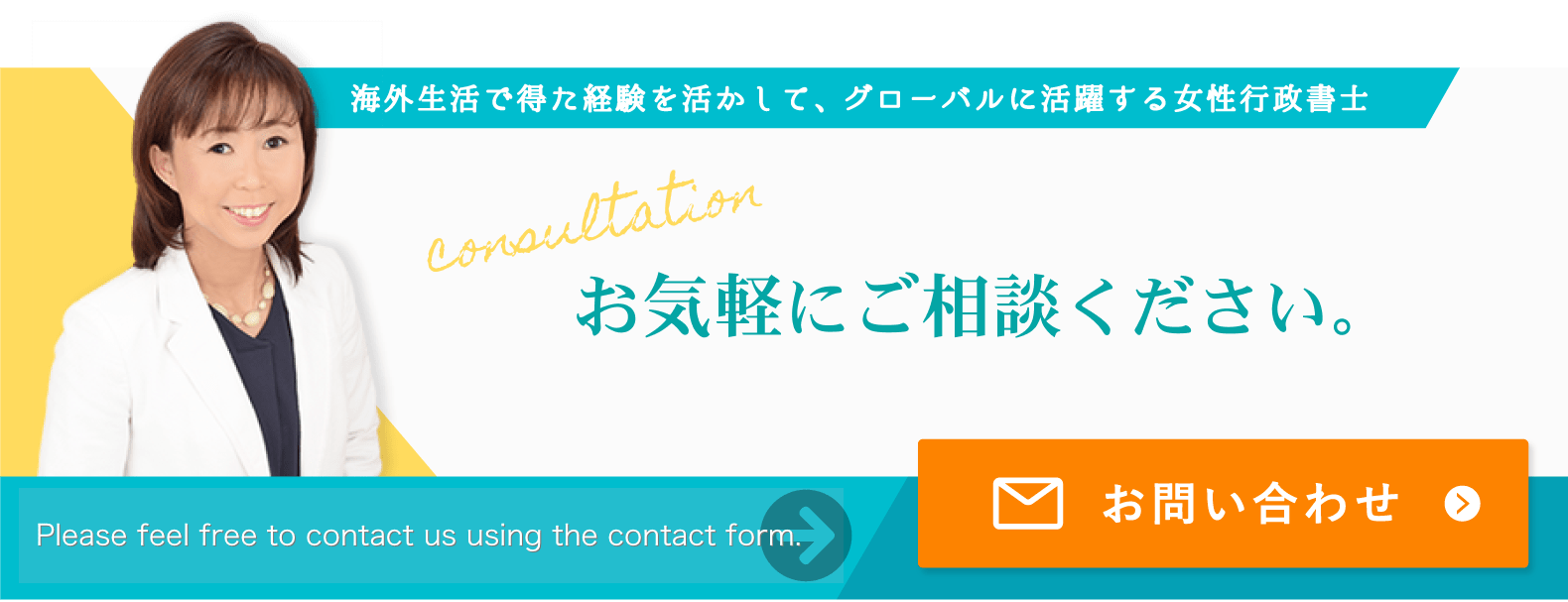帰化が認められる条件とは?

2020,03,03
こんにちは。
申請取次行政書士の伊藤亜美です。
前回の記事 帰化と永住権、何がちがうの?に続き、今回は帰化の要件についてわかりやすく解説致します。
帰化の要件
帰化には国籍法第5条による以下の6つの条件があります。
ただし、これらを満たしていても、申請が必ずしも認められるわけではありません。法務大臣の比較的広い裁量が認められているからです。
- 住所条件
適法な在留資格に基づき、帰化の申請時までに5年以上継続して日本に住んでいることが必要です。
- 能力条件
年齢が20歳以上で、本国においても成人年齢に達していることが必要です。
2020年4月以降は18歳以上になります。
- 素行条件
素行が善良であることが必要です。
犯罪歴の有無、納税状態など様々な要素が総合的に考慮され、社会通念によって判断されます。
交通事故についても過去5年間の違反経歴を審査されます。駐車違反など比較的軽微な違反であれば、5回程度までは問題ないとされるようです。
また年金についても2012年7月の法改正により、年金を払っているかどうかも審査ポイントになっています。年金を納めていない場合、帰化の条件を満たしません。
会社員の多くは厚生年金が会社で給料天引きされていることが多いと思います。されていない場合は、国民年金に加入している必要があります。
会社経営者は会社として厚生年金に加入していること、また従業員も厚生年金に加入させていなければなりません。
個人事業主は国民年金に加入していること、従業員5名以上の雇用がある場合は厚生年金に加入していなければなりません。
年金をはらっていない場合、さかのぼって未納分を追納することで、申請は可能とされています。目安としては一年分の追納です。
- 生計条件
生活に困ることがなく、安定して日本で暮らしていけることが必要です。
申請者自身の収入の他、配偶者などの収入や資産などで安定した生活を送ることができれば、条件を満たすことになります。
- 重国籍防止条件
原則として帰化によってそれまでの国籍は失われます。
例外として、アルゼンチンなどのように本人の意思によって本国の国籍を喪失することができない場合には、二重国籍の状態が生じてしまう場合であっても、帰化が許可になる場合があります。
無国籍の方も要件を満たします。
- 憲法遵守条件
日本政府を暴力で破壊することを目的とする団体を結成したり、加入していないことが必要です。
- 日本語能力
他の要件と違って、国籍法に日本語能力は明記されていません。
つまり日本語能力は帰化申請において法的要件ではなく、実質的要件です。
目安としては日本人の「小学生低学年レベルの読み・書き・会話能力」「日本語能力試験3級(N3レベル)といわれています。
特別永住者や15歳未満の方以外は、帰化の理由を自分の言葉で書いた「動機書」の提出が必要です。この動機書は直筆の手書きです。
他にも、宣誓書を読み、自分でサインしなければなりません。また、帰化の相談時や担当官との面接時にも日本語能力が試されます。
最後に
帰化許可申請は行ってから実際に許可を受けるまで、約1年かかります。
不許可認定を受けた場合であっても、再度申請することも可能ですが、その場合になぜ不許可になったのかを確認し、その点を解決したうえで再申請を行わなければ、再度不許可認定を受ける可能性が高いので注意です。
条件を満たしているかわからないなど、帰化についてのご相談はAmie国際行政書士事務所へぜひご連絡ください。帰化申請のカウンセリングから申請書類作成、法務局への同伴などトータルでサポートしています。千葉や東京を中心に帰化申請のご依頼を多くいただいております。帰化申請をご検討中の方は是非ご相談ください。
プロフィール
伊藤亜美
・東京都出身
・高校時代をイギリスで過ごし、現地校を卒業
・上智大学外国語学部英語学科で主に異文化コミュニケーションを学ぶ
・卒業後はメーカーの海外部門に11年間勤務
・高校生に英語を10年以上指導 TOEIC 970点 国連英検A級
海外で生活したことで、異なる文化の中で生活・仕事をする大変さを知り、日本で勉強したい・働きたい外国人や、外国人を雇いたい企業様のお役にたちたいと思い、行政書士の資格を取りました。
人と話すこと、話を聞くことが好きです。丁寧にお客様の状況をヒアリングし、法律の知識を活かして、最良な方法をご提案いたします。また、お客様とのコミュニケーションを丁寧にすることで、お客様が不安を抱くことがないように心がけています。
News and Blog