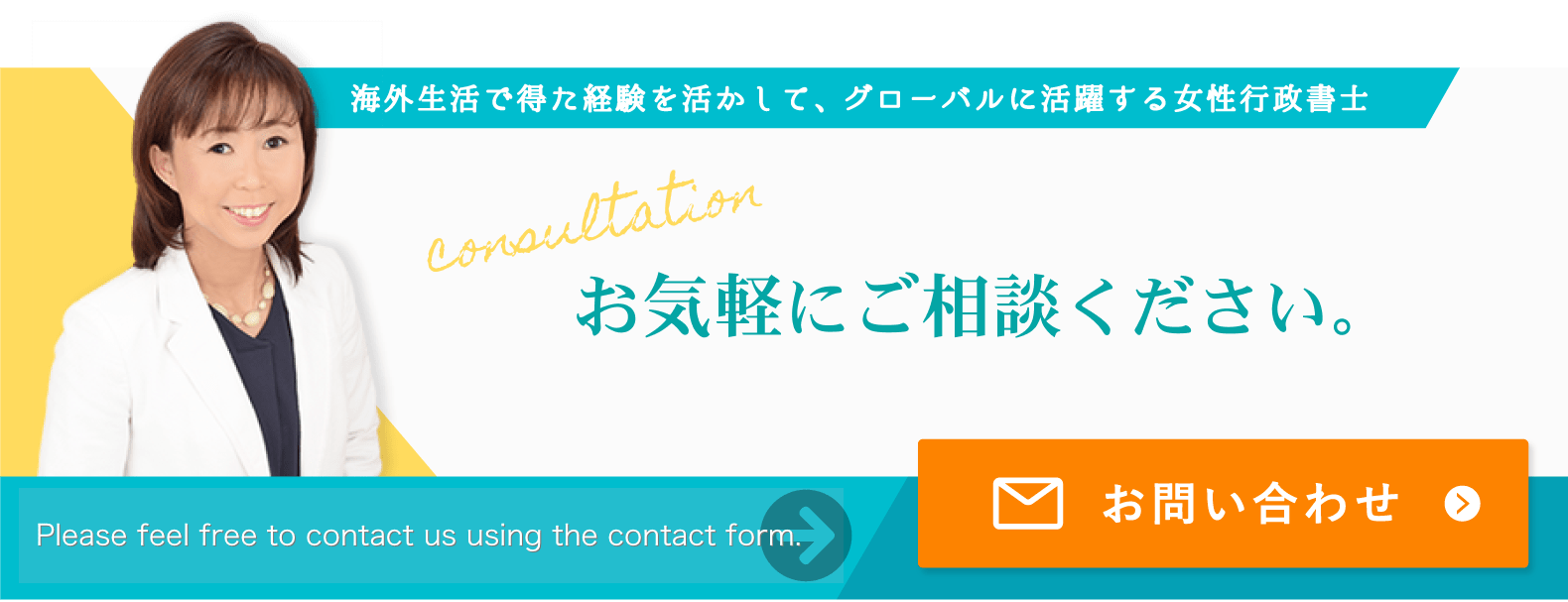同性婚とパートナーシップ制度

2023,10,24
This article in English What is a Partnership System?
パートナーシップ制度とは
日本の法律では性別が同じ者同士の同性婚を認めていませんが、一部の自治体で同性カップルの宣誓を受理する「パートナーシップ制度」を設けています。2015年に東京都渋谷区議会が初めて渋谷区パートナーシップ証明書を出す条例を制定しました。2023年4月時点で、パートナーシップ制度を導入した自治体は270を超えています。
同性カップルが日本で生活する際は、パートナーシップ制度を導入している自治体に住むことで生活がしやすくなる可能性があります。
自治体によって違いはありますが、申請することによって、証明書やカードが交付されます。
パートナーシップ制度で得られること
パートナーシップ制度は婚姻とは違い、現在は自治体が独自に設けている制度なので、法的な効果はありません。そのため同性婚のような法的な強制力はなく、あくまで市や県や市などの自治体が2人の関係性を認めるという形になっています。その結果、パートナーシップ制度によって得られるものは自治体によっても違います。代表的なものを紹介します。
住宅ローンサービス
2人で住む部屋が見つからないという不安に対して、パートナーシップ制度を活用しているカップルには、一部の大手メガバンクでもペアローンで住宅ローンを組むことができるようになってきています。
LGBT理解促進 性的マイノリティへの理解と対応【三井住友銀行】https://www.smbc.co.jp/aboutus/sustainability/employee/diversity/lgbt/
住宅ローンの連帯債務型借入における配偶者の定義に、「事実婚」「同性パートナー」を加え、同性パートナー向け住宅ローンの取り扱いを2020年2月より開始。
みずほ銀行
https://www.mizuhobank.co.jp/release/pdf/20171019release_jp.pdf?rt_bn=fb180117
東京都渋谷区が発行するパートナーシップ証明書の写しを提出すると、家族ペア返済や収入合算において、同性パートナーを配偶者の取り扱いを2017年7月より開始。
公営住宅への入居が可能

公営住宅への入居を認める自治体が増えてきています。入居資格の一つに「現に同居し、または同居しようとする親族があること。」とありますが、パートナーを親族と同様に取り扱う自治体が増えてきています。これまで「親族」と認められるためには婚姻関係や戸籍上の家族である必要がありましたが、同性カップルなどでも入居条件を満たすことが可能になってきています。
生命保険の受取人指定が可能
死亡保険の受取人に指定できるのは、原則として「配偶者または2親等以内の血族」です。しかし、保険会社によっては、自治体が発行するパートナーシップ証明書を提示することで、同性パートナーを受取人に指定できる生命保険もあります。 渋谷区のパートナーシップ制度の導入を皮切りに、様々な生命保険会社が同性パートナーを受取人に指定できるよう改めた保険をだしています。
例えばライフネット生命では2015年から同性のパートナーを死亡保険金の受取人に指定可能となっています。
https://www.lifenet-seimei.co.jp/rainbow/
生命保険会社によって契約時に必要な書類など詳細が異なるので、事前に保険会社に確認が必要です。
病院で家族として対応が可能

これまで家族として認めてもらえないために、パートナーが入院した時の病院での面会や看取りを断られるケースが多くありました。パートナーシップ制度を利用することで、症状の説明、救急車への同乗、緊急連絡先の指定、面会や治療方針・手術の同意等、退院時期と退院先の相談、救急搬送証明の申請、 リハビリテーション実施計画書に関する同意などが可能になる公立病院や民間の病院が増えてきています。
例えば大阪府堺市の「堺市パートナーシップ宣誓制度」では、市の医療機関に対して「パートナーシップの関係にある方の面会や手術の同意を患者が病院に求めることができます」と明記されています。
https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/jinken/jinken/sakaipartnership.html
まとめ
パートナーシップ制度は、自治体独自の制度です。活用するためにはカップルが同じ自治体に住んでいることが条件になります。引っ越しの際には、転出・転入先の自治体間が連携協定を締結している場合、転入・転出にかかる手続を簡素化されるケースもあります。
また、法的な効力がないのでパートナーシップ証明書を取得していても、民間の場合は対応するかは企業や病院の判断になります。しかし自治体がこのような制度をつくり推進していくことで、民間でもこの制度に対応する企業や病院が増えていき、社会的に浸透することが期待されています。
当事務所では同性婚パートナーのビザ申請をお受けしています。許可実績もあります。このビザは日本では許可されたケースが少ないビザです。経験のある当事務所に、ぜひ、ご相談くだ
プロフィール
伊藤亜美
・東京都出身
・高校時代をイギリスで過ごし、現地校を卒業
・上智大学外国語学部英語学科で主に異文化コミュニケーションを学ぶ
・卒業後はメーカーの海外部門に11年間勤務
・高校生に英語を10年以上指導 TOEIC 970点 国連英検A級
・千葉県行政書士会・国際業務部担当理事、申請取次委員会委員
・金融庁の 「外国語対応可能な士業のリスト(行政書士)千葉県」 にも正式に登録されています。
海外で生活したことで、異なる文化の中で生活・仕事をする大変さを知り、日本で生活したい・働きたい外国人や、外国人を雇いたい企業様のお役にたちたいと思い、行政書士の資格を取りました。
人と話すこと、話を聞くことが好きです。丁寧にお客様の状況をヒアリングし、法律の知識を活かして最良な方法をご提案いたします。また、お客様とのコミュニケーションを丁寧にすることで、お客様が不安を抱くことがないように心がけています。
お客様の声のページへ
News and Blog